
2025年7月12日(土)東海市立市民活動センターにて、3Rお片付けセミナー「ラクしてすっきり!実家のお片付け~3Rで生前整理・住まい再構築~」を開催いたしました。5回目となる3Rセミナー。今回のテーマは「いつか向き合う必要のある実家のお片付け」。
・忙しすぎて先延ばしにしていた ・家族の協力が得られない、など様々な理由でスムーズに進められないご家庭が多いのが現実です。
放置していたために急な判断を迫られ、その結果「家庭ごみの大量廃棄」や「分別できずに資源を有効活用できない状況」を生み出してしまいます。3Rを活用したメソッドでごみ問題だけでなく、家庭内でのもめごとも解決できる、たくさんのコツを教えていただきました。
【講師】 RE-CREATE SYSTEM.(リクリエイトシステム) 成田宮子さん
片付けを通して空間を最適に整え、時間と利益を生み出す整理事業“リクリエイトシステム”を立ち上げ、個人宅・スモールオフィスの片付け及び生前整理に取り組んでいる。セミナー等による啓蒙活動でも活躍中。分かりやすく人に寄り添ったセミナーが好評。
家族と協力して片付けるコツ
◆なぜ、モノと向き合えないのか◆
「片づけができずに、モノをため込んでしまう家族の背景には、物理的環境問題と心身の問題が複雑に絡み合っています」と成田さんは言います。「捨て方がわからない」「高齢で思うように片付けられない」…など負の連鎖で増えていくのは、モノとしての価値がなくなった「死蔵品」です。継続的に片付けを進めていくためには、モノに対する価値観が異なる家族に、歩み寄る工夫が必要となってきます。
◆どうしたら動いてもらえるのか◆
ここからは「やってはいけない事の具体例」と「NGとなる声かけ」について学びました。ただモノを減らすことだけがゴールなのではなく、最終的にどんな暮らしがしたいのかを双方が共通してイメージすることで、ようやく協力し合えるスタートラインに立つことができるのです。

環境創りの3STEP
基本となる「環境創りの3STEP」に沿って、どう動いていくべきかを整理しながら、お話を伺いました。例えば重要なステップとなる「仕組み創り」においては、終活ならではの介護ベッドの置き場の確保や取り出しやすいモノの配置について取り上げました。
大切なのは、これらの課題を「身体が動くうちに自分で決める」ということ。基本を理解したら、次は家の中にぎっしりと詰まったモノの仕切り直しです。抱えている全てのモノを4つのカテゴリに分類することで、今の自分にとって必要なモノが何なのかを判断していきます。
理想の未来へ近づけるための片付け手順

家族をサポートしながら進めるお片付け。ここからはサポートする側の心構えと効果的な声かけなど、具体的なアプローチについて学びました。
重要なことは、「相手の気持ちにフォーカスする」こと。モノが多い人は不安を多く抱えていることが多いそうです。「大切にしたいモノは?」「私も片付け始めたから一緒にやろう!」安心感を与えられるような、そんな一言を伝えながら進めていきましょう。
部屋の使い方の見直し
どんな暮らしを目標(ゴール)とするのかが分かったら、次は具体的な段取りを考えます。身体が衰えてくることを考慮しながら生活パターンの見直しも含めて考えていく必要があります。「重要書類の管理は?」「洗濯物を干す場所は?2階→1階?」など、サポートする家族が知っておくべき情報も出てくるでしょう。
不用なモノを手放す
部屋(入れ物)の使い方を決めたら、いよいよ中身(家の中のモノ)を分類していきます。予め自治体のごみや資源の出し方も把握しておきましょう。
また、片付けにはお金がかかるもの。3Rを活用したお片付けの大きなメリットとして、資源として手放すことでごみ処理費用を安く抑えられる点があげられます。3Rを知ればお得に片付けれらるだけでなく、苦手な「捨てる」が楽になったり、感謝してモノを手放すことができるようになるのです。
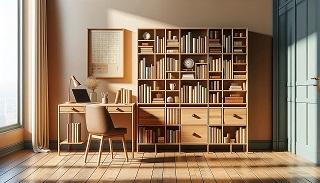
継続的に進められるコツの1つに、「できた!」「気持ちいい」の小さな成功体験があげられます。ポイントは1時間程度で作業が終わる場所から手をつけること。その場で選別できず、処分に困るモノは一時保管するなど無理をしない工夫も必要です。家族が選別できず作業が滞ることがあっても、けして無理強いはせず、この段階でも安心できる言葉かけをしていきましょう。

また、家族の認知機能の低下も考慮することが必要です。勝手に処分されたと思い込む被害対策として、分かりやすい収納を心がけましょう。「使用頻度」や「行動動線」などを考えながら、使いやすく配置することがポイントです。
東海市でのリユースの取り組み
東海市では、不用品を資源として役立てる取り組みを行っています。実家のお片付けで大量に出やすい本や未使用のタオルなど、寄付として活用できるモノもたくさんあります。地域情報サイトを活用したリユース活動もぜひ活用してみましょう。詳しくはこちら
まとめ
家の中には、これまで生きてきた人生の集大成がぎっしり詰まっています。長期的な関わりが必要なのも当然と言えるでしょう。しかしモノと一旦向き合うことで得られる効果も高いと言えます。死蔵するのではなく、生きたモノの使い方をすることで、本当に必要なモノだけに囲まれた暮らしを手に入れることができます。
ごみになるモノを持たないリデュース。次に必要とする方に価値あるうちに譲るリユース。そして地球上の大事な資源として役立てるリサイクル。
サポートする側もされる側も元気なうちに、環境に配慮したお片付けを始めてみませんか?
セミナー当日に配布したアンケート内に記載の、「3Rを活用したお片付けにまつわる質問」について、成田さんから順次ご回答いただき、動画にて掲載して参ります。詳しくはこちら(暮らし再創作 YouTube)
